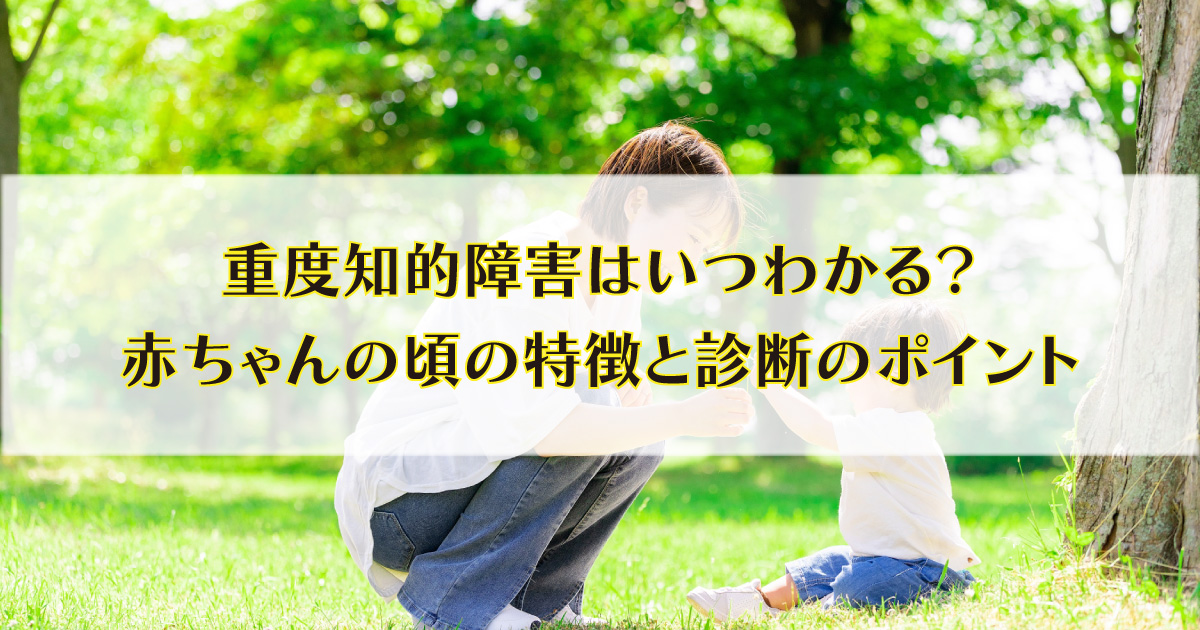お子さんの発達が他の子と比べて遅れているように感じたとき、知的障害があるのではないかという不安に駆られることがありますよね。
私も息子が1歳になる頃、呼びかけに反応しなかったり、目が合わないことに違和感を覚え、悩んだ経験があります。その時の不安はとても大きなものでした。
この記事では、重度知的障害の子の赤ちゃんの頃のサインや、具体的にいつ頃(何歳頃)に診断がつくのか、と言った内容を詳しく解説します。
診断を受けることは不安かもしれませんが、早期診断により適切なサポートを受けることで、子どもの成長を安心して見守ることができます。
私自身も不安でしたが、早めに動くことで心が軽くなり、より前向きに子育てを進めることができました。
同じような悩みを抱えるママさんたちにとって、この情報が少しでも役に立ち、次の一歩を踏み出すきっかけになればと思います。
Sponsored Links重度知的障害とは?|初期のサインと特徴について

重度知的障害の定義と特徴|軽度・中度との違いを知ろう
重度知的障害は、軽度や中度に比べ、発達の遅れが目立ち、日常生活で多くの支援が必要となる状態です。
軽度知的障害の場合、子どもは言葉や日常生活である程度のやりとりが可能で、サポートを受けながら少しずつ自立に向かうこともあります。
中度の知的障害では、日常生活に一定のサポートは必要ですが、自己管理や基本的な会話が可能なこともあります。
一方、重度知的障害の子どもは、言葉がほとんど出なかったり、自分の意思を伝えることが難しく、常に大きなサポートが必要です。
赤ちゃんの頃に見られる兆候|1歳半までに気づくポイント
赤ちゃんの頃から、重度知的障害の兆候が現れることがあります。
例えば、目が合わなかったり、呼びかけに反応しない、笑顔が少ないなどの行動が見られることがあります。また、1歳半までに言葉が出なかったり、おもちゃや周りの物に興味を示さない場合も注意が必要です。
ただし、こういったサインが見られても、すぐに知的障害があると判断できるわけではありません。迷った場合には、役所の発達相談窓口や児童相談所などの専門家に相談するといいでしょう。
他の発達障害との違い|自閉症と知的障害の併発について
重度知的障害は、自閉症スペクトラム障害(ASD)と併発することがあります。
ASDは、社会的なやりとりやコミュニケーションが苦手だったり、感覚が敏感であることが特徴ですが、知的な遅れがない場合もあります。
しかし、ASDを持つ人の約 30%から50% が知的障害を併発していると言われています。知的障害を伴う場合、学習や日常生活のサポートがより多く必要になります。
知的障害の有無によって、ASDの子どもに対するサポート内容も異なってくるため、適切な支援を早期に受けることが重要です。
重度知的障害はいつわかる?|診断のタイミングと専門家の役割

判定はいつから可能?|早期発見の大切さ
重度知的障害の判定は、1歳半健診や3歳児健診での発達チェックがきっかけとなることが多いです。
健診では、「言葉が遅れている、目が合わない、呼びかけに反応しない、指差しができない」といったサインが見られると、「要観察」となることがあります。
実際、私の息子も1歳半健診で要観察となり、その後2歳0ヶ月の時に保健センターへ相談しました。すぐに療育を開始し、3歳半で児童相談所にて重度知的障害と判定されました。
私の周りを見ても、3歳から5歳頃に重度知的障害と判定される子が多いように感じます。
1歳半の健診で「様子を見ましょう」となることも多いのですが、この時点で何も問題がないことは少ない為、発達の遅れが気になる場合は早めに専門機関へ相談することをお勧めします。
早期に支援を始めることで、子どもの成長をサポートできるチャンスが広がります。
診断が遅れるリスクとは?|早めの対応が大事な理由
診断や判定が遅れてしまうと、療育やサポートのスタートが遅れるため、子どもの成長に大きな影響を与える可能性があります。
特に重度知的障害の場合は、早期の支援が子どもの発達に良い影響を与えることが多く、言葉やコミュニケーション能力の向上を期待できます。
私も息子の療育を早めに始めたことにより、支援を受ける中でさまざまな成長のサインを感じられました。
支援が早いと親の不安も軽減され、適切なサポートを受けることができるので、安心して育児に取り組める環境が整います。
どの専門機関に相談すればいい?|安心してサポートを受けるために
もし1歳半健診や3歳児健診で「要観察」と言われた場合、まずは児童相談所や発達支援センターに相談してみるのがおすすめです。
私の息子の場合も、保健センターを通じて早めに療育が始まり、3歳半で児童相談所にて重度知的障害と判定されています。
専門機関では、発達に関する詳しい検査や評価が行われ、その後、療育施設や保健センターでのサポートを紹介してもらえます。
少しでも気になる点があれば、早めに専門家に相談することで、子どもにとって最適な支援を受けられる道が開かれます。
早期に適切なサポートを受けることで、親も子どもも安心して日々を過ごせるようになります。
重度知的障害の原因|わかることとわからないことの違いとは?

原因が明確なケースと原因不明のケース|知っておきたい背景
重度知的障害の原因について、はっきりしている場合もありますが、残念ながら多くのケースでは原因がわからないことが多いです。
親として「なぜ我が子に?」という疑問や不安を抱えることは、自然な感情です。しかし、その責任を親自身が感じる必要はありません。
現在の医療では、すべての原因を解明することが難しいこともあり、親が「できる限りのこと」を考え行動していること自体が、何より大切な一歩です。
重要なのは、どのような背景であれ、子どもの成長を支えるために適切な支援を早めに受けることです。
育児の中でできるサポート|親ができることとは
我が子の発達に不安を感じたとき、親として何をすべきか悩むことがあるかもしれません。
成長がゆっくりと感じられる場合は、早めに対応したいという気持ちが湧くのも自然なことです。
どんなに小さな疑問でも、早めに相談することで、子どもにとってより良いサポートを見つけるきっかけになるかもしれません。
日常生活では、子どもの興味を引き出すためのコミュニケーションや遊びを通じて成長をサポートできます。
特に、発達が遅れていると感じた場合でも、無理に急がせるのではなく、親子で楽しみながら一緒に成長を見守る姿勢が大切です。
また、周囲のサポートを得ることや、専門家に相談することで、親自身の不安も軽減され、子どもへの向き合い方にも自信が持てるでしょう。
親が安心してサポートすることで、子どもも安心して成長できる環境が整います。
重度知的障害を持つ子どもへのサポート|家庭でできることとは?

家庭でできる支援方法|遊びや日常のサポートを通じて発達を促す
重度知的障害を持つお子さんにとって、日々の家庭でのサポートはとても大切です。特に、遊びや絵本を通じてコミュニケーションを取りながら成長を促すことは、楽しみながらできる方法です。
おもちゃや絵本を選ぶときは、年齢ではなく、今のお子さんの発達に合ったものを選ぶのがポイントです。子どもが興味を持てるように、シンプルな仕掛けのおもちゃや、わかりやすい内容の絵本が良いでしょう。
親子で一緒に遊ぶ時間は、子どもにとって大切な成長の機会です。リズム遊びや絵本の読み聞かせ、指や手を動かす遊びを通じて、自然と感覚を育てていきます。
さらに、毎日の生活の中での小さな成功体験が子どもの自信を育てます。たとえば、スプーンを使って食べる練習や、片付けを手伝ってもらうことで、「できた!」という達成感を感じさせてあげましょう。
親が楽しんで一緒に関わることで、子どもも安心して成長していくことができます。小さなステップでも、毎日の積み重ねが大きなサポートになるのです。
療育施設やプログラムの活用|早期介入で成長をサポート
家庭でのサポートに加え、療育施設や専門プログラムを活用することも、重度知的障害を持つ子どもの成長を支える大切な方法です。
療育施設では、専門家が一人ひとりに合った支援を行い、子どもの発達を手助けしてくれます。早い時期にサポートを受けることで、子どもが社会性やコミュニケーションの力を身につけることが期待できます。
施設では、子どもの発達状況に応じたプログラムが用意されていて、個別指導やグループ療育を通じて成長をサポートします。子どもが自分に合ったペースで少しずつ力を伸ばすことができるのです。
さらに、親も施設でのアドバイスを活かして、家庭で実践できるサポート方法を学ぶことができます。
施設と家庭が一緒になって子どもの成長を見守ることで、子どもが安心して過ごせる環境を作ることができるのです。
子どもの将来の展望|学校生活から卒業後の支援までの不安とサポート
重度知的障害を持つ子どもを育てる親にとって、学校生活も将来も不安はつきものです。
学校では、子どもに合わせた支援を受けながら成長を見守ることができますが、それでも「うまくやっていけるかな?」と心配になることも多いですよね。
そして、学校を卒業した後は、さらに不安が大きくなるかもしれません。卒業後の生活では、就労支援施設や生活支援センターなどが、社会に出た子どもをサポートしてくれます。
たとえば、就労支援施設では仕事のスキルを身につけたり、生活支援センターでは日常生活の支援をしてもらえます。
親としては、早めに卒業後に利用できる地域の支援施設の情報を集めておくと安心です。
子どもが将来、社会の中でサポートを受けながらも成長していけるよう、少しずつ準備を進めることが、親の不安を和らげる第一歩になります。
まとめ|不安に寄り添いながら次の一歩へ進むために

お子さんの発達に不安を感じると、どうしていいか悩んでしまうことがありますよね。
まだ診断がついていなくても、「何かできることはないか」と心配するのは自然なことです。そんなときは、まずは支援が受けられる場所を見つけて、専門家に相談することが大切です。
ちょっとした不安や疑問でも、話してみることで新しい情報やサポートが見つかるかもしれません。
ひとりで悩まずに、早めに相談することで、気持ちが少し軽くなり、親としての心の余裕も生まれます。
不安を感じたときこそ、少しずつでも動き出してみてください。あなたの一歩が、お子さんの成長を支える大切な力になるはずです。